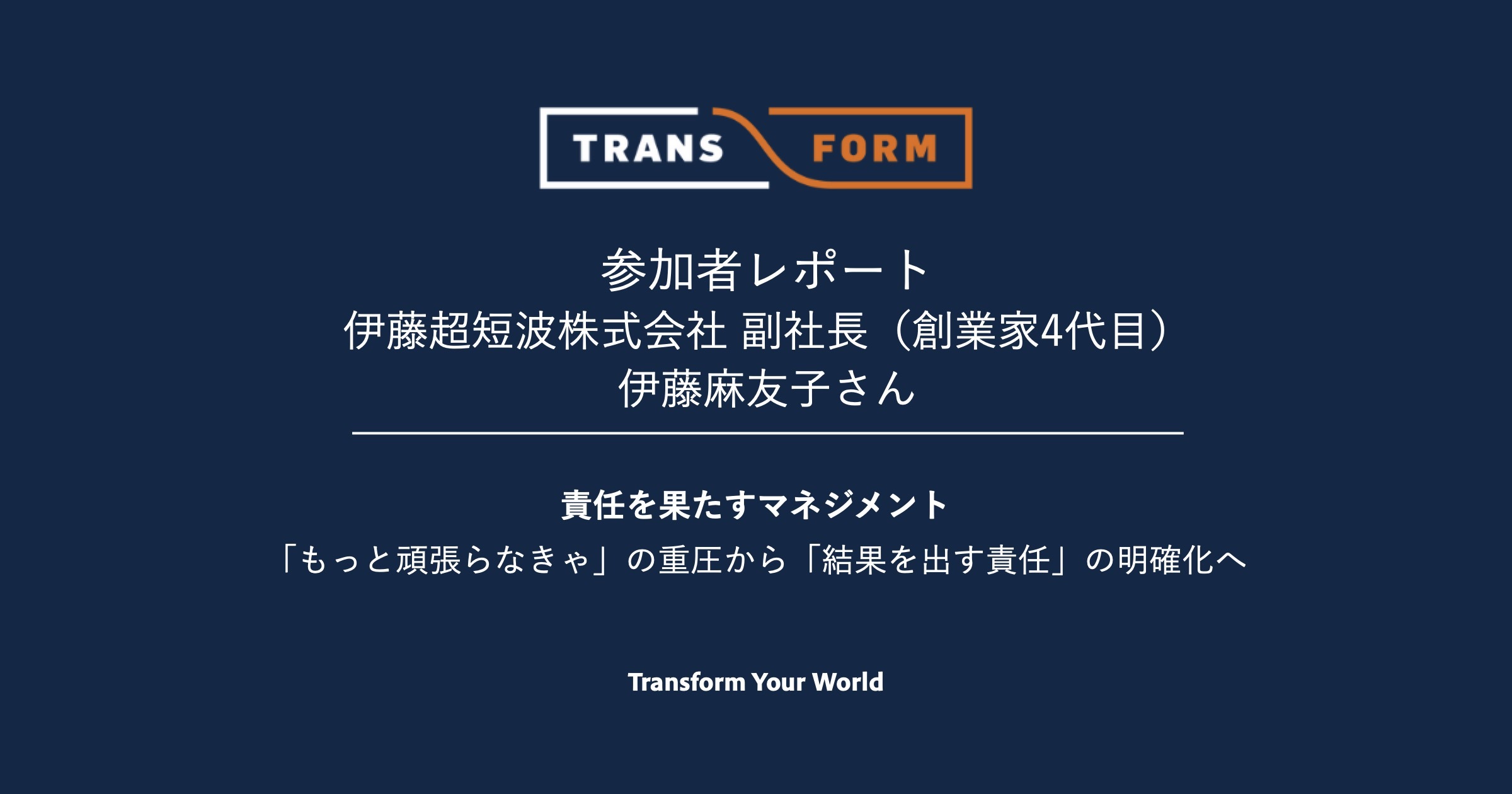
参加者インタビュー:「もっと頑張らなきゃ」の重圧から「結果を出す責任」の明確化へ
責任を果たすマネジメント
― 「もっと頑張らなきゃ」の重圧から「結果を出す責任」の明確化へ
創業して100年を超える伊藤超短波株式会社の4代目として副社長を務める伊藤麻友子さん。
経営と組織変革を担う立場として日々多くの決断を重ねるなかで、彼女は2017年の年末からTransformのプログラムに継続的に参加し、学びを深めてきました。
本記事では、伊藤さんがどのようにして「マネジメントとしての本質的な責任」に向き合いながら、自分自身を見つめ、組織のリーダーとして日々の変化のなかで前に進んでいるのか、というプロセスをご紹介します。
変化の始まり:外に答えを探していた私が、自分の現在地に気づいた
伊藤さんがTransformのプログラムに出会ったのは、「何かを変えなければ」と感じながらも、次々と立ち現れる課題に対し、「どこから手をつけたらいいのか…」と迷いの中にいた時期のことでした。
もともと家業を継ぐつもりはなく、キャリアのスタートはクリエイティブ系やIT系のベンチャー企業。自由で風通しのよい環境のなか、自分の意見を出しながらやりがいを感じて働いていたといいます。けれど、キャリアを重ねてチームや部下を持つようになると、少しずつ「どうチームを運営したらいいのだろう?」「どこまで踏み込めばいいのか?」といった悩みが増えていきました。
伊藤さん「もともと人とのコミュニケーションには苦手意識があって。ミーティングのあとも、あれでよかったのかなと一人でぐるぐる考えることが多かったです」
その後転職を経て、現在の会社に入社。従業員300名を超える歴史ある企業(創業家)で、経営者としての新たな挑戦が始まりました。けれど、それまでのベンチャー企業で経験してきたスピード感や柔軟さとはまったく異なる文化に、当初は戸惑うことも多かったといいます。
伊藤さん「外から来た自分にとっては、なぜそれが当たり前になっているのか分からないことばかりで、異世界に来たような気持ちになることもありました」
ちょうどその頃、ビジネススクールで組織論やリーダーシップを学び、「このままではいけない」という気持ちは強くなるばかり。学びを現場で活かそうとするものの、思うようにいかず、気がつけば「変えたいのに、何をどう変えたらいいのかわからない」と、行き詰まっていたそうです。
「もっと本を読まなきゃ、もっと勉強しなきゃ」と焦る気持ちだけが先走り、休日に本を買い込んでも読めずに落ち込むことの繰り返し。やればやるほど空回りしているような感覚に、徐々に疲弊していきました。
そんな中で出会ったのが、Transformのプログラムでした。
参加の背景には、「まずは自分の内面から課題を見つけよう」という意識がありましたが、それは、理不尽な経験や環境の転機を経てたどり着いた「境地」のようなものでもあったと伊藤さんは語ります。
なかでも印象的だったのが、「レッドゾーン・グリーンゾーン・ブラックゾーン」という概念との出会いでした。
伊藤さん「自分が今どのゾーンにいるんだろうってことがよりはっきり分かるようになったのがすごく印象的です。」
これまで漠然としていた自分の状態を、「今はレッドに近い」「いまは少しグリーンに戻ってきた」と言語化できるようになったことは、伊藤さんにとって大きな発見だったといいます。
「まずは自分の現在地を知ること」。その一歩から、伊藤さんの変化は少しずつ始まっていきました。
苦手だった内省――変化の感覚はそこから始まった
Transformのセッションで重視される「チェックイン」や内省的なエクササイズは、伊藤さんにとってはいまだに「苦手」だと感じている部分。
伊藤さん「自分自身を見つめるというのは、苦手なことや避けている課題だったんです」
Transform稲墻 「自分自身と向き合うことが難しいというのは、向き合いたくないという感じですか?」
伊藤さん「多分そうだと思います。少し面倒な気持ちもありますし、何か⾒えるのが怖いんだろうなって思います」
また、プログラムの中でこれまでとは違う選択や行動を取ることで、「なんか違うあり方」「違う意思決定」「違う選択」が自分の中に出てくる感覚に、戸惑いを感じることもあるそうです。
変化の入り口に立ち、これまで慣れ親しんだ自分のあり方を手放し、新しい在り方に移行していくとき——そこには心地よさとは異なる、ある種の「揺らぎ」が生まれます。そしてそれは普通のことと言えます。
マネジメントの根源的な問い:責任とは何か
伊藤さんは最近、「マネジメント」に焦点を当てたプログラム(Transform特別プログラム:「選択肢を広げ、イノベーションにつなげるマネジメント」〜マネジメントは管理ではなく創造である〜)に参加しました。その中で、マネジメントの役割について大きな気づきを得たといいます。
伊藤さん「マネジメントというのは、結果を出す責任があるということ、あとは、人を活かして結果を出すということ」
これまでは、自分が努力することでなんとかしようとしていた部分もありましたが、「それだけではどうにもならない領域がある」ということを実感。人を通じて結果を出すことこそが、マネージャーの責任であると理解したそうです。
さらに、以前は「責任感が強い自分」という認識を持ち、よかれと思い自分が大きな責任を負いすぎていたいた伊藤さんですが、このプログラムを通じて、「責任感」と「責任を果たすこと」はまったく別のものである、ということにも気づきました。
伊藤さん「責任感は強い方だと思っていましたが、責任を果たすということと、責任感を持っているということは、全然別物なんですよね」
波風を立てる勇気。調整型からの脱却
伊藤さんはこれまで、「波風を立てずにうまくやること」を大切にしてきたといいます。
もともとコミュニケーションには苦手意識があり、「誰かに何かを言われると、身構えてしまうところがある」と語ります。
伊藤さん「あまり反応的に発言することはほぼないので、できるだけ相手の話を聞くようにしてきました」
そうした姿勢が、結果として大きな衝突を避けることにはつながっていたものの、「波風を立てないことだけを優先していても、物事は変わっていかない」という葛藤も抱えていたそうです。
Transformでの学びを通じて、伊藤さんの中で少しずつ変化が起きていきました。
特に「マネジメントの責任とは何か」を深く見つめ直したことで、自分が担う役割をより明確に意識するようになったといいます。
その結果として、これまではためらいを感じていたような難しい対話や判断が求められる場面にも、一歩踏み出せるようになってきました。
伊藤さん「自分の責任は何かを意識するようになってからは、伝えるのは簡単ではないけれど、結果として伝えることができたと感じています」
以前であれば、状況に圧倒されて頭の中でぐるぐる考え続けてしまっていたような場面でも、マネジメントの責任を意識することで、最近では少しずつ「割り切れる」ようになってきたといいます。
次世代へのメッセージ:共通言語を広げ、よりよい世界へ
今後に向けて、伊藤さんが個人として深めたいと感じているのは、「自分の中では気づけているものの、まだ動けていないこと」に一歩踏み出し、実践していくこと。
そして、自分自身だけでなく、会社の中にも共通言語を持った仲間を増やしていくことを、次のテーマとして挙げています。
Transformのプログラムで得られた一番の学びとして、伊藤さんは「対話」の価値を強調します。
同じ問題意識を持ち、同じ前提のもとで深く考える場は、一人ではなかなかつくれない。だからこそ、その時間と空間が非常に貴重だったと振り返ります。
伊藤さん「一定の共通言語や、同じ前提で話せる人がもう少し増えると、会社も良くなると思いますし、そういう人が増えていけば、きっと世界はもっとよくなっていくんじゃないかなと思っています」
この言葉の背景には、「いろんなものの見方ができるようになると、自分自身も楽になり、選択肢にも気づけるようになる」という、伊藤さん自身の体感があります。
最後に伊藤さんは、マネジメントにおいて大切にしている視点をこう語ってくれました。
「当たり前のことをやるのって、実はすごく難しい。でも、テクニックやセオリーに走る前に、『そもそもマネジメントって何だろう?』という問いに立ち戻ることが大事だと思っています」
伊藤さんの言葉には、役職や肩書きを超えて「人」として真摯にマネジメントと向き合ってきた深さと、そこからにじみ出るやわらかな力強さがありました。
伊藤さん、お忙しい中、快くインタビューを受けていただきありがとうございました。
プロフィール
伊藤麻友子(いとう まゆこ)さん
創業1916(大正5)年の医療機器メーカー、伊藤超短波株式会社の創業家4代目。代表取締役副社長として経営および組織変革を推進されています。2017年末よりTransformプログラムに継続的に参加し、社内での共通言語の拡大とサポートシステムの構築を目標とされています。

